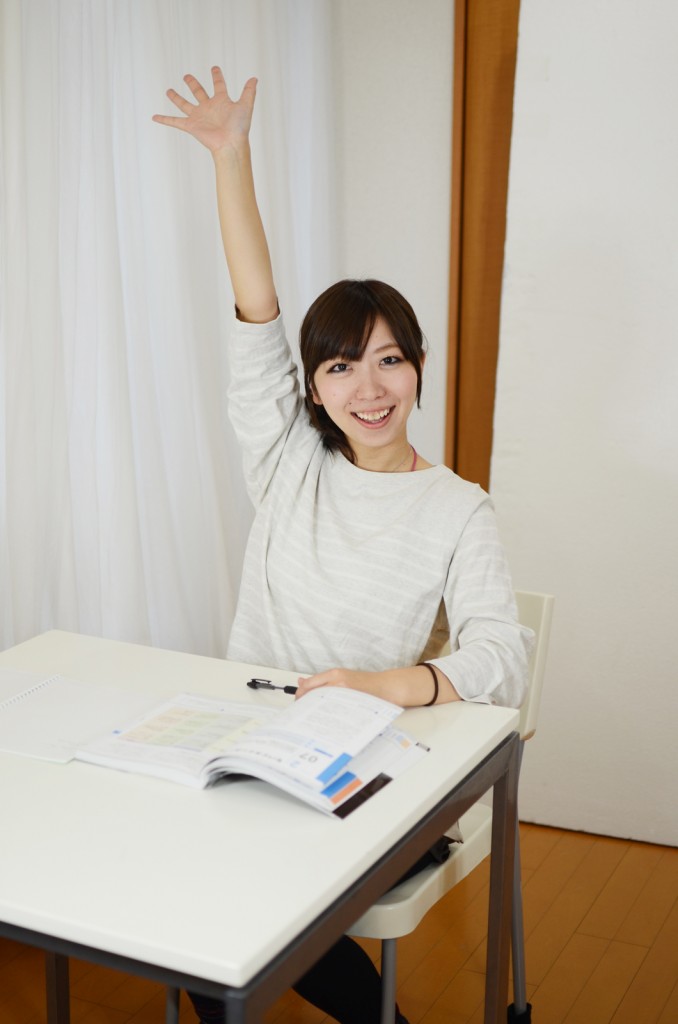簿記はどのように学ぶのが良いのでしょうか。
ここでは、日商簿記検定が代表的検定ということもあり、それを念頭にしたいと思います。
他の全経簿記や全商簿記も、出題内容はほとんど同じと考えてよいと思います。
まず出題内容としては1級以外は、ほぼパターンが一定しているようです。
4級はごく基本といえ、簿記を習うとは「3級」からスタートすることを意味すると言ってよいと思います。
資格スクールも3級を基礎としてそこから講座を展開しています。
3級、2級と進むのが一般的でしょう。1級以上やるかどうかは、その方の判断がありますね。
級により学習量がやっぱり違います。
大体大手スクールの講座量と期間の例としては
3級で週2日(1講座2時間30分) を2ヶ月 (14章くらいになっています)
2級で週2日(1講座2時間30分) を2ヶ月商業簿記、さらに2ヶ月工業簿記 (14章ずつくらいになっています)
といった感じ。
単純にいえば、3級を基本として、2級は2倍ですね。
1級はさらに週3回(1講座2時間30分) 6ヶ月 ぐらい。やはりチャレンジですね。
これからだいたい勉強時間の目安もわかります。もちろん講座を習っただけでは、合格できるほど甘くはありません。
特に復習して、手で覚える必要があります。
勉強の仕方としては、
まず 専門用語の意味をおさえ、処理(しくみ)を理解します。
次に基本例題があるので解き、記憶します。
そして問題集で実践力をつけ、過去問をやる。
それをまわすことですね。
スクールなどで習う場合、初めのうちは復習を基本にしてよいのではと思います(賛否両論あるかもしれませんが)。
私が講師の方に教わったのは、
「簿記は頭で考えるものではない。手で習う。問題を解く」ということでした。
「習うより慣れよ」ということなのです。
それから、簿記は正確さとスピードを意識していくこととよいですね。
事務という仕事自体が正確さとスピードというある種矛盾したことを求めるわけですが、
経理もそうです。
他の事務も簿記を持っているほうが望ましいのは、この「正確さとスピード」ということを簿記で鍛えられているから
ではないでしょうか。
検定試験自体も「正確さとスピード」が求められます。
「電卓」も早く打てるようになったほうがいいですね。
これは練習するうちに皆さん早くなるようです。
速くて正確って「かっこいい」ですよね。